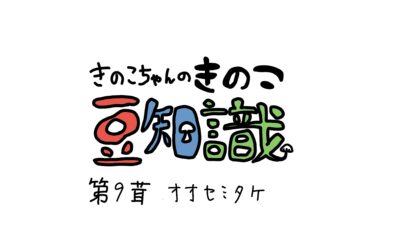きのこ豆知識 分類から見る「菌類」という生きもの
「きのこ」は動物?植物?それとも…
はじめに、皆さんの食卓でも見ることができるであろうきのこたち。今パッと思い浮かんだのはシイタケ、エノキタケ、エリンギなどなど…。そんな食用のきのこたちは、いつも食料品の「野菜コーナー」で見られると思いますが、きのこは植物ではありません。そして、動物でもありません。
きのこは「菌類」なのです。
「菌類」という生きものは「動物」でも「植物」でもないきのこ・かび、酵母などを含んだ生物群です。菌類は陸上、水中あらゆる環境に生息しており他の生きものを分解したり他の生きものと共生したり、寄生したり…と自然界において重要な働きをしています。(↓↓↓きのこ豆知識「きのこの役割」参照)

私たちがよく見ている「きのこ」の部分。傘があってヒダがあって柄がある。またはお茶碗形のものもいれば棒のような姿のものもいます。
それらの部分は「子実体(しじつたい)」と呼ばれ、胞子をつくるいわゆる「種(たね)」の部分なのです。一方、普段は目にする機会が少ないきのこの根っこの部分。根っこの大半は土や木の中で暮らしている「菌糸(きんし)」なのです。菌糸はよく見てみると、クモの巣状の糸があちこちにはびこっています。これらは、枯葉や動物の死がいなどを食べているもの、または生きている植物と共生(助け合って生きている関係)している「きのこの本体」なのです。


担子菌門(たんしきんもん)
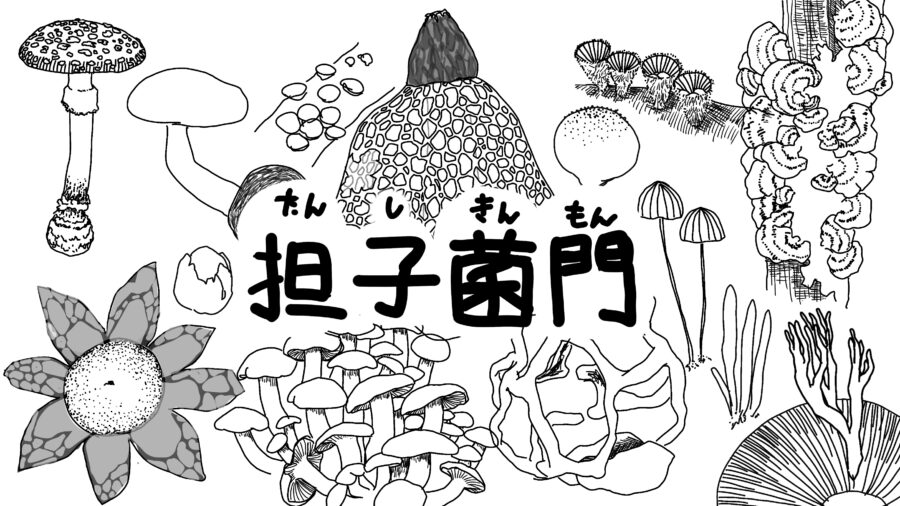
担子菌門に所属する菌類は、担子器(たんしき)と呼ばれる構造の外側に胞子をつくる菌類で子実体を作る仲間と作らない仲間(さび菌、くろぼ菌など)があります。また、私たちがよく見たり、食べたりしているシイタケ、エリンギ、キクラゲなどはこのグループに所属します。
- ハラタケ目
- イグチ目
- キカイガラタケ目
- コウヤクタケ目
- タマチョレイタケ目
- イボタケ目
- タバコウロコタケ目
- スッポンタケ目
- ラッパタケ目
- ヒメツチグリ目
- キクラゲ目
- アンズタケ目
- アカキクラゲ目
- シロキクラゲ目
- サビキン目
など

いわゆる「きのこ形」をしたものが多くヒダ状がほとんど。

「きのこ型」をしているものが多く管孔状(小さな穴が集まっていてスポンジ状の裏側)がほとんど。

「きのこ型」をしているものが多くヒダ状、中には乳液を出す種類もいます

木材から生えていることが多く、質感は硬めの種がほとんど。

菌根性の種類が多く、地面から生えている姿を見かけます。形は「サンゴ型」「ラッパ型」などさまざま。

比較的新しい枯木に生えていることが多く、ゼラチン質でぷにぷにしています。
※ 日本産のものはアラゲキクラゲではなく、ナンカイキクラゲと同一とする見解もあり、今後学名が変更される可能性があります。(参考論文はこちら 表題は参考欄にかいています)

枯木に生えていることが多く、ゼラチン質でぷにぷにしています。

サビキン目は植物の病原菌として知られており、さまざまな植物の葉や枝、花など種類によって発生場所が異なります
子嚢菌門(しのうきんもん)

子嚢菌門に所属する菌類は、子嚢と呼ばれる袋状の内部に胞子をつくります。この仲間には子実体をつくる仲間とつくらない仲間があります。ちなみに、世界三大珍味のトリュフや、人気が高いアミガサタケ(モリーユ)などはこのグループに所属しています。
- ボタンタケ目
- クロサイワイタケ目
- ビョウタケ目
- リチスマ目
- ウドンコカビ目
- チャシブゴケ目
- イワタケ目
- エウロチウム目
- テングノメシガイ目
- チャワンタケ目
- ヒメカンムリタケ目
など

ホオノキの古い果実(集合果)から黒い子実体を生やします。

シイの落ち葉(特に葉柄や主脈付近)に生える小型の菌類です。梅雨の時期によく見られます。

地衣類(ちいるい)として分類されています。藻類と菌類が助け合いながら生きていて、街中、里山、高山など様々な場所で観察することができます。

地中に住んでいる種類や枯木に生える種類が知られています。丸型や棒型などきのこに見えない形が多いです

全体的に黒っぽいものが多く、地面から棍棒状の子実体を伸ばします。

お茶碗型や丸型、網型、鞍型などさまざまな形をしています。

タフリナ科の菌類が引き起こす伝染病です。感染木は桜の花が咲く頃でも緑色の葉がでているのでよく目立ちます。外国では「魔女のほうき」と呼ばれています
接合菌門(せつごうきんもん)
動物の糞や植物などに生えるとても小さな菌類です。接合菌門の仲間には、昆虫やその他の節足動物に寄生するものも知られています。
- ハエカビ目
- ケカビ目
など


きのこに寄生する菌類の一種。時には宿主を覆いつくすくらいふわふわになることがあります
グロムス菌門
グロムス菌は、草木の根と共生しアーバスキュラー菌根をつくるため農業への応用研究が進んでいます。この種類のいくつかは胞子が集まって肉眼でもわかるくらいの子実体をつくります。

【参考書・論文・webなど】
小学館の図鑑NEO きのこ(小学館)
身近な菌類の観察(神奈川県生命の星・地球博物館)
菌類のふしぎ(東海大学出版部)
日本産“Auricularia auricula-judae”および“A. polytricha”の分子系統解析と 形態比較に基づく分類学的検討(論文)